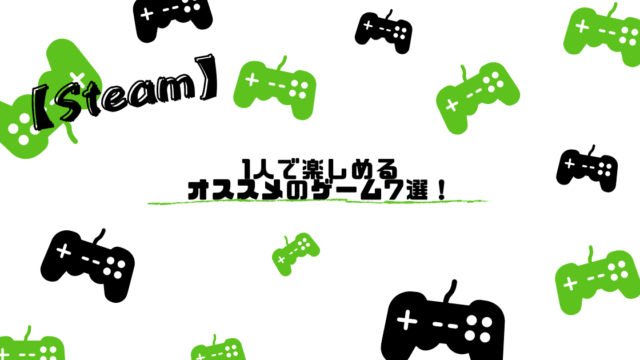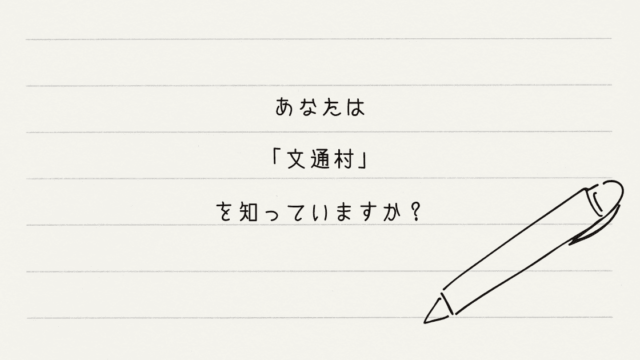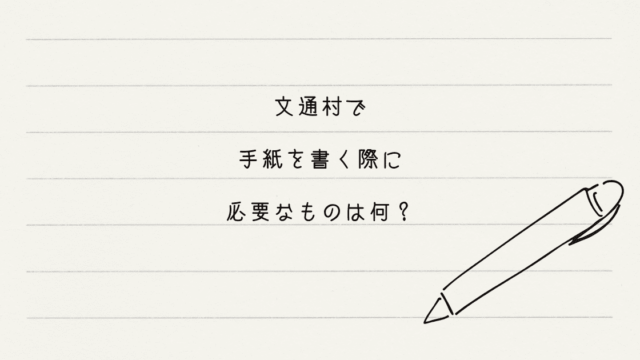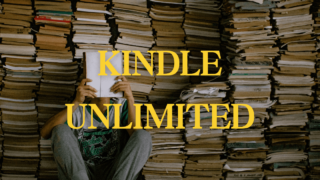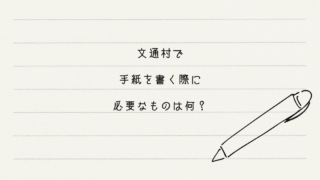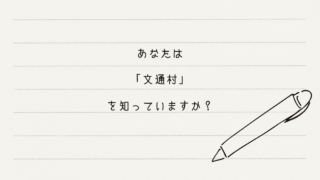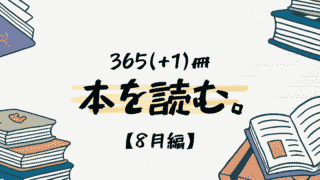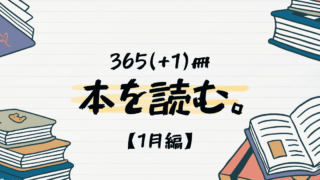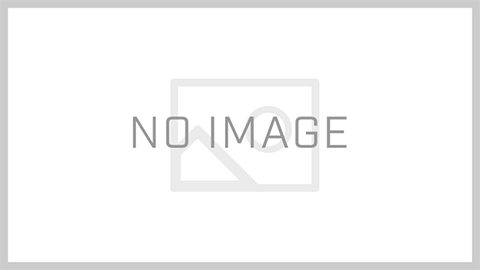【辞典】開いたページの知らない言葉(1)
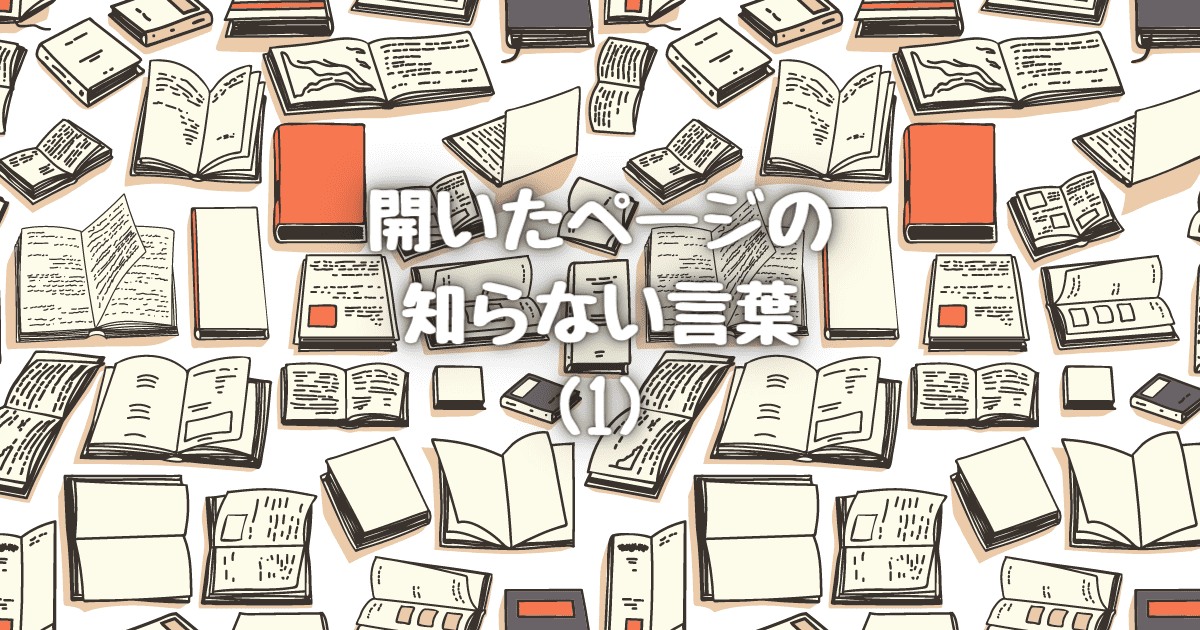
現代に生きるどれだけの人が紙の辞典に触れているのか?
全く検討もつきませんが、きっと少ないことでしょう。
必要があれば、スマホでささっと簡単に検索出来てしまいますし。
でも、紙の辞典には、紙の辞典ならではの良さってものがあると思うんですよね。
紙の絵本や小説、新書、ライトノベルなどと同じように。
この記事では、そんな風に考えている私が「ここだ!」と開いた辞典のページの知らない言葉を紹介します。
よろしければご覧ください。
今回使用する辞書はこちら
『新明解国語辞典 第七版 特装青版』になります。
私が初めて自費で、自らの意思で購入した辞典です。
どのような動機で購入に至ったかは全くもって覚えていないんですが、何故だか猛烈に欲しくなって衝動買いした記憶があります。
皆さんも思わず買ってしまった辞典がありましたら、是非教えてください。
P.578の知らなかった言葉 7選
正直な所、辞典を開いて、ページを直接目にするまでは「そんなにないかもなー」と思っていました。
しかし、今回の知らなかった言葉の総数はなんと19。
自らの思慮の浅さを恥じ入るばかりです……。
今回はそんな言葉の中から厳選して、7つの言葉を紹介します。
もし時間が許すようなら、ご自身が知っているかどうか是非チェックされてみてください。
さしぢち【差(し)乳】
㊀乳の出ない母親に代わって乳を与えること。また、その人。
㋥お椀を伏せたような、形のよい乳房。さしぢ。〔よく乳が出るものとされる〕
『新明解国語辞典 第七版 特装青版』三省堂より引用
初っ端から全くもって耳にしたことの無い言葉。
現代の日本においては、最早㊀の方の意味合いで使うことは、中々無いかもしれないと感じました。
私の見識の狭さ故の考えであれば、失礼。
㊁の方の意味合いについては、きっと使えなくもないのでしょう。
ただ、実際どのような場面で使うのか……。
仲睦まじい男女間のやり取りの中で使う?
……ううん、ちょっと無理がありそうです。
さしつかわ・す【差(し)遣(わ)す】
〈自分の代理として〉人を行かせる。
『新明解国語辞典 第七版 特装青版』三省堂より引用
この言葉は何だか日常で使えそうです。
「大変申し訳ございません、少々立て込んでおりまして……。代わりに〇〇を差し遣わせますので。どうか、よろしくお願いいたします。はい、はい。失礼いたします。……ふぅー」
のような。
でも、ちょっと偉そうというか、責任転嫁感があるので、個人的にはあんまりこういった風には使いたくないかもしれません。
何か不自由があって、にっちもさっちもいかないときに、申し訳ない気持ちを感じつつ、言葉に出来たら適切でしょうか。
さしつぎ【指(し)継(ぎ)】
〔将棋で〕前回から持ち越した勝負を続けること。
『新明解国語辞典 第七版 特装青版』三省堂より引用
この言葉はどうでしょう。
将棋を日ごろから嗜む方であれば、割と使われたりされるのでしょうか。
私は一応将棋を指せますが、残念ながら知らず……。
「今日差し継げる?」なんてラフに使えたら、ちょっとカッコイイですね。
相手に通じるかどうかは分かりませんが。
さしつぎ【刺(し)継(ぎ)】
布地の弱った所を(同質・同色の)糸で刺して補強すること。
『新明解国語辞典 第七版 特装青版』三省堂より引用
前の言葉と同音異義語になります。
漢字が1つ異なるだけで、意味が全く変わってしまうのってすごいですよね。
日本語を学ぶ外国人の方からすれば、厚切りジェイソンさんが叫ばれるあの言葉を、内心で静かに叫びたくなるやもしれませんが……。
ただ、この言葉に関しても、使われる機会はあまり無いんじゃないかなと思いました。
そもそもそういったシーンが生まれれば、今を生きる日本語を解する多くの人は繕うのではなく、新しい服を購入することを選択するでしょうから。
私含め。
そんな中で「刺し継ぐ人」がいたら、なんだかそれは素敵なことですね。
さしつめひきつめ【差(し)詰(め)引(き)詰(め)】
〔昔の戦闘で〕弓に矢をつがえては引きしぼって、続けざまに矢を射かけ、激しく攻め立てる様子。
『新明解国語辞典 第七版 特装青版』三省堂より引用
この言葉はもう、現実世界の中では「使われることのない言葉」と言ってもきっと差し支えないでしょう。
それほどに平和になった、と捉えることが出来れば、使われなくなるという良さも生まれてくるのかもしれません。
もちろん、物語中においては不滅ですが。
そう捉えると、物語が存在する価値って凄まじいですね。
いつまでも言葉を未来に運んでいくという点で。
さしまえ【差(し)前】
自分が差している刀。差し料。
『新明解国語辞典 第七版 特装青版』三省堂より引用
こちらも最早、現実では使われることはないのでしょう。
気になるのは、当時の人がどのような感覚でこの言葉を使っていたのか、ということ。
「お主の差し前、マジ卍」
帯刀している状況が続いていたのなら、こんな話し言葉が聞こえてくることもあったのでしょうか。
さしば【翳】
薄絹などを張ったうちわ状のものに長い柄を付けたもの。従者がかざして貴人の顔を隠すのに用いた。
『新明解国語辞典 第七版 特装青版』三省堂より引用
「差し歯」の漢字1文字バージョン?
と思いましたが、全く違う意味でした。
アニメやドラマなどで、時折目にすることのあるあの道具にこのような名前があったとは……。
辞典を開かなければ、私はこの言葉を知らないままに命を終えていたかもしれませんね。
最後に
ここまで『新明解国語辞典 第七版 特装青版』のP.578に記載のあった、私が知らなかった言葉を7つ紹介いたしました。
どこの馬の骨とも知らぬ人間の知らない言葉を知ったところで、どこの誰に得がある?
と書きつつ思いましたが、書いていて面白かったので、私個人としては満足。
もし、何かしら「へえ」なり「ほぉん」なり、参考になっていましたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。